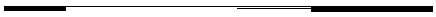私の係は場内警備係である。係名は厳めしいが、所定の場所に交代で立っていればいいだけの仕事だ。所謂、関係者以外立ち入り禁止の貼り紙の前で、通せんぼをする係だ。しかし関係者は皆IDカードをぶら下げているので、関係者以外の人間は近寄ってこないし、IDカードのない者は通れないと言うと素直に従ってくれる。ボランティアに日当が出るのはおかしな話だが、これでも一日千百円の手当と弁当が付くのである。
試合は近隣の少年サッカーチームのベスト8を招待したトーナメントだ。市政百周年の記念イベントと言っても、観客もスタッフも全員関係者のようなものなので、参加者は皆お行儀がいい。悪さをする子供もいないし、酔っぱらいの親父もいない。その日、朝早くから、私は大きな紙切れのIDカードを首からぶら下げて、観客席と本部席の境界に立っていた。ゲームが始まっても特に興味もないので、ろくに試合も見なかった。しかし、異様な歓声がにわかに沸いたので、フィールドを見た。Kが颯爽としたスーツ姿で手を振って、市民の喝采を浴びていた。開会式には間に合わなかったからしいが、かといって、試合中に姿を見せては選手たちの集中力が切れてしまうのに。
スタジアム裏手にある関係者入退場口の付近にはちょっとした人だかりがあった。スポンサーのご厚意で選手と役員は試供品のドリンクを自由に受け取ることができる。交代で取れる休憩時間に、私は試供品のドリンクを貰いに行った。赤と白の派手なパラソルの下で、やはりボランティアで市に駆り出された高校生たちが接待係として笑顔でドリンクを配っている。
その高校生たちの中に、色白で清楚なイメージのする女の子がいた。一瞬、私は胸のときめきを感じて年甲斐もなく赤面した。他人のそら似には違いないのだろうが、私の高校の同級生にそっくりだったからである。自分の全てに自信が持てなくて、臆病だった私にはクールな優等生タイプの彼女とはまるで接点がなかった。一度も言葉を交わしたことがないまま、自分の思いを一方的に胸の奥にしまい込んでいた。その彼女とそっくりな女の子がいきなり目の前に現れたのである。
子供たちの列に混じって、ドリンクをタダでもらえる列に親父が並んでいるのを何とも気恥ずかしく感じた。元気な小学生が生意気に憎まれ口を叩きながら、缶ジュースを彼女の手からもぎ取るように奪っていく。後ろの子供に背中を押されて、私の番が来た。
「それください。」
「はい。」
彼女は氷水の中に手を入れて、私が指さした青いアルミ缶を取り出して、右手で持った布巾で丁寧に水を拭き取ってくれた。キーンと冷えた缶を受け取り、小さく礼を言う。私は振り返ることもできないで、そのままその場から立ち去った。彼女はきっとこんな声だったのかもしれない。彼女が私のために発してくれた「はい。」の一言が、私の中で反響していた。
「浅岡純」という名札の姓には心当たりはなかったが、彼女の娘か親戚か。いや、わからない。とにかく似ていた。どきどきする。何度も何度も同じ女の子からドリンクをもらうのは不自然だ。いやしい親父とも、いやらしい親父とも思われたくはない。二本目をもらいに行くのは躊躇われる。でも大会は二日間、どうせ明日までだ。係が少ないのか、人がよいのか、浅岡純は私がその近くを通りかかる度に、いつもその席にいた。小学生のサッカー試合を見たいとは思わないかもしれないが、こんな係にずっと貼り付き通しなのはかわいそうな気がした。
疲れ切って自宅に戻る。息子のチームは一回戦を無事突破し、明日の準決勝に駒を進めることになった。フェイスペインティングの剥がれかけた妻の顔が、はしゃいでいる分、余計に老け込んで見えた。