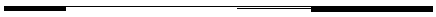最終日の役員集合時間にスタッフルームを注意深く見回すと浅岡純が友達に囲まれて隅の方に控えている。やはり高校の時の同級生にそっくりだ。話しかけてみようかと思ったが、これと言って話題があるわけでもない。いきなり父親くらいの年齢の男に声をかけられたら戸惑うだろう。役員の全体朝礼や、係ごとの打ち合わせが終わり、スタッフはそれぞれの持ち場に散った。私は主に観客席と本部席の境界に立っていたが、今日も大した仕事はなさそうだ。
息子チームの試合にはそれでも注目はしていたが、結局、準決勝も補欠のままに終わりそうだ。妻は朝早くからサポーター気取りで燃えていたけれども、息子のサッカーセンスが大したことないくらい、私の方がよく見抜いている。審判の笛が鳴り響いた。息子チームは私を含めた周囲の予想を覆して決勝戦に駒を進めることになった。
浅岡純はずっと係席でドリンクを配っている。係席のすぐ後ろで昼の弁当も食べていた。ひっきりなしに子供や大人がやってくるので忙しそうだった。私は純のところへドリンクをいつ貰いにいこうか考えていた。「それください。」「ハイ。」以外に純と会話がしたい。しらじらしく「ご苦労様。どこの高校の人。」と声をかければよいだけなのだろうが、私の心はいつの間にか、かつてのニキビ面の純情少年にすっかりと戻っていたのである。
決勝戦が始まった。これが終わる頃にはドリンク配布所も撤去してしまうだろうから、いつまで躊躇っていられない。ふと、私の目の前を通り過ぎた女性スタッフのTシャツの背中に誰かのサインがあることを発見した。Kのサインだ。Kは今日も本部の来賓席に来ている。表彰式に出て、優勝カップを渡す役目があるのだろう。
私は来賓室のドアが見える廊下の入り口に立って待っていた。ドアが開いてKが廊下に出てきた。私の横を通り過ぎて洗面所へ行く。決勝戦の後はすぐに表彰式なので、廊下にいればKに会えると思ったのだ。タイミングを見計らって洗面所に入る。鏡の前で整髪しているKに思い切って声をかけた。
「Kさんですよね。息子がファンなんです。こんなもので失礼かと思いますが、サインをいただけませんか。」
私がKに差し出したのは自分のIDカードの裏面だった。Kは屈託のない笑顔でそれを受け取ると営業用のスマイルを見せる。さらさらとサインを書きながら、私の顔など見ようともしない。
「息子さんも試合に出ていらっしゃるんですか。」
「いえ、うちの奴はまだ補欠ですから。」
Kに頭を下げてカードを受け取り、そそくさと私はその場から逃げ出した。
「それください。」
やっと回ってきた順番。私は浅岡純の前に立っていた。彼女は元気よく「はい。」と返事をして昨日と同じ青いアルミ缶を氷水の中から取りだしてくれる。私は宝物を自慢する時の子供のようにKのサインを彼女に見せた。
「もらっちゃったよ。ほら。」
彼女はアルミ缶を拭きながら、怪訝そうな顔でそのサインをのぞきこんだ。
「Kのサイン。今、本部席のところにKがいたもんだからさ。」
「えーっ。すごいですね。いいなぁ。私ずっとここにいなくちゃいけなかったんで、まだKさんを見てないんです。いいなぁ……。はい、どうぞ。」
「ありがとう。大変だね。忙しくて…。よかったら、記念にこのサインをあげるよ。」
私はIDカードを首から外して純に差し出した。純は目を丸くして素直に喜んでくれる。
「えー。いいんですか。ありがとうございます。嬉しいです。大切にします。」
隣にいた同じ係の高校生が露骨に羨ましがった。純が友達に囲まれているのを見ながら、私はそっとその場を立ち去った。
延長に入ってから、息子は決勝戦に出場した。息子の出したボールがゴール前に転がり、キャプテンがダイレクトにシュートを決めてチームはめでたく優勝した。キャプテンがKから優勝カップを受け取り、それを中心にチーム全員がKと一緒に記念の写真に収まった。
その夜の食卓。
妻は私が息子の活躍シーンを見ていなかったことを責めながらも、上機嫌で酒の肴を作ってくれている。棚の上には浅岡純のくれた青いアルミ缶がある。私はキーンと冷えた缶ビールを飲みながら、Kのアシストで手に入れたささやかな思い出を見つめていた。