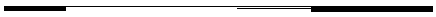夢の続きを見たことはない。
アクション映画の主人公になったような夢、恋愛映画の主人公になったような夢。しかし、それがどんなに楽しい夢であっても、さぁこれからという時に夢から覚めてしまい、悔しがる。その続きをいくら見たいと思って布団に潜り込んでも、見ることは不可能だ。同じ設定の夢ならばよく見る。夢の中では、自分の年齢や環境はいつも同じだ。子供の頃によく見た夢の中にあった町並みは今も変わらない。
学生の時にアパート暮らしをしていたが、当時の夢もよく見る。社会人となっている今の自分が、昔のアパートを訪ねる。なぜか自分の部屋が昔のまま今もあるので驚く。自分は賃貸を解約しないで来てしまったのか。もしも大家が滞納している分の部屋代をまとめて払えと、請求してきたら払えるのだろうかと、その部屋に立ちつくしてドキドキしてしまう。そんな他愛のないパターンの夢だ。
またその夢を見た。ところが、いつもの通りに自分のアパートを尋ねると、部屋が廃墟のように古ぼけている。壁紙がはがれ落ち、襖が破れ、天井が落ちていて、陽の光が斜めにさらさらと差し込んでいる。家具が埃で白茶けて見える。どうしたんだ、一体。気が動転して、外に出ようとすると玄関の郵便受けに目が留まる。自分の消えかかった名札のついた箱に一枚の葉書が入っている。取り出してみると確かに自分宛だ。持つ手が震えた。差し出し人の名前を見るまでもない。懐かしい文字が耳元で自分の名を囁いた気がした。
彼女と知り合ったのはある劇団の入団テストだった。大学は違うが、歳も同じ、同じ学部で、住んでいるアパートも近くだった。お互いテストには落ちたけれども、恋にも落ちた。蜜月はそれこそ夢のように過ぎ、卒業のシーズンが近づいた。地元での就職を条件に四年間の都会暮らしを許されていた自分と、都会を離れず自分の夢にこだわる彼女。もう一度、自分から連絡をすればよかったという後悔だけが、心に苦く残っていた。
葉書には「私の部屋を尋ねてほしい。」とだけ書いてある。靴を履くのももどかしく、アパートを飛び出した。町の風景は学生街のままだ。つけが残っている酒屋、気のいい親父のいた食堂、腕時計をなくした銭湯、出来たばかりのコンビニ。バイトの子が可愛かった喫茶店。今日も煙草屋のばあさんは居眠りをしている。走馬燈のような景色を背景に、息を切らして懐かしい街を駆け抜ける。大きな給水塔のある角を曲がると彼女のアパートが見えるはずだった。
夢から覚めた。
今も都会で暮らしている友人に久しぶりに電話をかけた。学生街のアパートはすっかり取り壊されて、高級マンションになってるという。給水塔の周りもバブル期の再開発ですっかり様変わりをして、更地のまま放置されているという話だった。あの頃の街はもうない。そして………。
夢の続きを見たことはない。