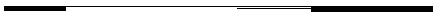中星隆徳は矢川圭と視線があってたじろいだ。
中星の背後から高中勇介が絶望じみた声でつぶやく。
「だから入るなって言ったのに」
六畳間の真ん中で矢川圭が座って編み物をしていた。制服のブラウスの上に、カーディガンをかけたという寛いだ服装だった。圭は編み物の手を止めて、中星をその大きな目で見て凍りついていた。中星はよろりと座り込む。勇介がドアを後ろ手に引いて閉めて、中星の隣に座り込んだ。そして短髪の頭をかきむしる。中星は大きく息を吐きながら室内を見渡す。
「お前たちが同棲していたとは……知らなかった」
圭が口をぱくぱくさせてから、それでも取り繕おうとする。
「な・か・ぼ・し・くん。私は、ただ隣に住んでるだけで……」
中星が笑いながら、両の手のひらを上に向けて、ひらひらさせた。
「馬鹿野郎。この部屋はなんだ。まるで新婚所帯だよ」
男子高校生の一人住まいとはとても思えない。格闘技のポスターが貼ってあるのが、むしろ調和を乱していているくらいだ。小物や壁掛け一つとっても、男子高校生の部屋にしては、中性的すぎる。
「勇介。お前、どうも下宿している割には友達を呼ばないと思ったら」
「悪い。中星。騙していた訳じゃ……あるんだけど」
「くっそう…。何が、コーチの言いつけで友達を下宿に呼ばないだよ。大嘘じゃないか。……うまくやってるな。お前たち」
その悪意のない爽やかな笑顔に圭はほっとして席を立つ。
「ありがとう。お茶入れるわね」
中星はあぐらを掻いて、部屋をきょろきょろと見回す。
「しかし、一体、いつから一緒に暮らしているんだ」
「四月からだよ」
「今年の四月か」
「いや、去年の」
「すごい。よく、今までばれなかったな……一年以上じゃないか」
勇介は大柄な体を小さくして、部屋の隅で溶けてしまいそうだった。中星の方もそわそわと居心地が悪く、落ち着かない。
勇介と圭が遊山荘に住み始めたのは偶然だった。両親が地方に転勤となって、転校を余儀なくされたのだが、高校生なのだから自立したいという願いを許されて、それぞれ一人暮らしを始めたというのが共通の発端である。つまり二人は同じアパートに住むまでただの同級生だったのだが、「同」じアパートに「棲」むうちに、二人の距離が縮まって「同棲」「同衾」することとなったのである。
不思議と世間や学校の目を逃れて一年半。あと半年で卒業という日まで、互いの友人を煙に巻きつつ暮らしてきた。しかし意外な伏兵、勇介のクラスメートの中星が強引に勇介の家に遊びに来てしまったのである。
「心配するなよ。誰にもしゃべりはしないよ」
圭が感激して夕食を作ってくれた。三人ともアルコールが入って、大いに盛り上がる。勇介が同棲生活の苦労を中星に打ち明け、中星もよせばいいのに、問いただす。
「で、二人ができたのは、いつだ」
圭は答えなかったが、勇介が悪のりする。
「それが半年かかった。なかなか固いんだよ、彼女は」
圭が恥ずかしがって、勇介をどつく。勇介がごろんと一升瓶をひっくり返す。中星が慌てて拾う。
「わっ馬鹿。勿体ない」
テーブルにこぼれた吟醸酒を啜ろうとする勇介へ圭のエルボーがさらに炸裂する。
「汚いことしないの」
「お前だって、するじゃないか」
「お客さんの前ではしないのよ」
こりゃあ、いい夫婦だ。中星は小声でぼやく。
中星はその日一宿一飯の恩義を被ることになる。
「俺がここで一人で寝る。二部屋借りてあるんだろう。勇介は圭と」
「いいから、お前は俺と寝ろ。圭が俺の部屋で寝な」
勇介たちは寝る時は圭の部屋を使っている。勇介の部屋には布団が一組しか置いてなかったからである。中星はすっかり酩酊して、勇介の話を遮る。
「いや、圭の布団で寝るのは悪い。」
「俺が圭の布団で寝るんだ。お前は俺の布団で寝ろ」
圭の部屋にある布団は二組だが、一組は勇介のものである。勇介は親が泊まりに来る時のために、二組の布団を持っていたが、勇介の部屋の押し入れが狭くて一組しか入らない。圭はもともと一組しか布団を持っていなかったので、押し入れにゆとりがあった。そこで勇介が親用の布団を一組預かってもらっていたのである。その辺りのやりとりが二人の仲が進展する始まりだった。何が切っ掛けになるか分からないのが、男女の仲。
中星はその夜、勇介の布団の中で嫉妬に狂いながら、なかなか寝付かれなかった。俺も彼女がほしい…隠しようのない本音だった。
大高校。文化部の部室長屋の最北端、演劇部の部室。バンシューとあだ名される部長、川村赤穂が中央の白い丸テーブル越しに、自称部長様の玉座と呼ぶ上座に、今日も今日とてどてんと座っている。バンシューは三年生であるので、部員としては引退の時期だが、しぶとく部室に通っている。下級生への引き継ぎは十二月というのが恒例なので、まだまだ頑張っている。と言いたいが、先ほどから、コテンと丸テーブルにうつぶせになって、顔を横に向け、小声で童謡を歌っているとは甚だ不健康な雰囲気である。演劇部は言うに及ばず、大高のスーパースターと一部では言われている彼女ではあるが、さては老化現象か。そこへ銭形平次捕物控であれば八五郎にあたる中星隆徳が部室のドアを荒々しく開けて飛び込んでくるのが、この物語のオーソドックスなパターンである。肩書きだけは副部長である中星だが、彼は一度も舞台に立ったことはない。別名、ミスター大道具である。その中星が勢いよく部室に飛び込んでくる。
「バンシュー、大変だ」
「なーにー」と顔上げもせずにバンシューは生返事をする。見向きもしない。
「そんなネコの子みたいな返事はするなよ。大変なんだよ」
バンシューはやれやれとようやく体を起こす。眠そうに背筋を伸ばす。確かに子猫みたいにやわらかい所作だ。
「だからニャンだってぇ」
「高中が死んだんだよ。そいで矢川もだよ。自殺だって」
バンシューは両手を合わせて合掌する。
「にゃむ阿弥陀仏」
中星は椅子にどっかりと腰を落ち着けてお手上げのポーズをする。
「それが、大高の女ホームズと言われたバンシューの反応かよ。あーん」
バンシューは頬杖を突いてよそ見をする。言っておくが、バンシューには探偵癖がある。くだらない事件に適当に介入して一応解決させるという奇特な女子高生だったのだ。実際に殺人事件を幾度か解決に導いたこともある。その名探偵が最近、事件に食傷気味なのてだろうか。今日はとんと調子が悪いようだ。
「よう、バンシュー」
「はいほい」と上の空。
「だから、圭と勇介が自殺したんだってよ」
「別に…関係ないわよ」
「かーっ。稀代のお節介バンシューが…信じられん」
「だってさぁ…、私はその二人とは話したこともないよ。名前と顔くらいは知ってるけどね。もう、私は探偵稼業は廃業したのさ」
バンシューは手鏡とブラシを持ち出して、前髪をいじり始めた。明らかに中星の話に乗り気ではないといった仕草である。
「探偵料をもらうわけでもないし。お礼言われた例しもないし。私はもう嫌ですよ。探偵ごっこは卒業よ」
中星はうなって、腕組みをする。とりつく島がない。しばし、沈黙が支配する。
そこへ放課後の追試が終わったらしく、多岐純紀が入ってきた。中肉中背のバンシューに比べると純紀はやせっぽちである。バンシューも美少女だが、純紀もかなりの美形。二人は演劇部の二大看板なのだから当然かもしれない。純紀にとって不運なのが、キャラクターでバンシューに負けていることだ。太陽のようなバンシューの前では、純紀は月みたいなものである。であるが、今日は勝手が違う。太陽は皆既月食中らしい。
「ねぇねぇ、バンシュー。圭ちゃんが自殺したんだって。知ってる」
バンシューは大きなため息をついて、鏡をぱたんと机に伏せる。
「んもーっ。やれ怪文書。やれ殺人。失踪。自殺。何だって私の周りの人たちは犯罪大好き人間ばっかりなのかしら。私はもう誰がなんと言っても探偵の真似事はしません」
バンシューがきっぱり言うと、純紀が笑いながら、横目でバンシューを見る。
「うっそーっ」
「本気です。あんたたちもあんまり事件に関わると内申書に響くわよ」
「あーら、バンシュー。芥川女子大の推薦入試決まったんじゃなくて」
バンシューは推薦入学で女子大に入学することが内定しているという噂だったが、バンシューはしばし凍り付いた後で糸の切れたマリオネットのように肩を落とした。顔を伏せたまま、小さな声でつぶやく。
「あれ。落ちちゃったの」
「内定は、決定だとか言ってたのはバンシューでしょうよ」
「指定校推薦の枠が去年まであったのに、今年はなくなってたのよ。公募推薦てのは落ちたりするんだって。小論文が理解されなかったのね。私の演劇論を理解できる大学教授はいなかったってことよ。今から受験勉強かと思うと、がっくりきちゃってさ」
バンシューが落ち込んでいたのは実に入試に滑ったからだったのだ。中星が新発見をしたように指をぱちんと鳴らす。
「その心の隙を埋めるのは事件しかないな」
バンシューは憎々しげな視線を中星に送り、観念したように手を挙げた。
「わかったわよ。話してご覧なさいよ」
発見者は遊山荘の大家、物見一郎という五十過ぎの男である。彼は二人が同棲していることは気づいてはいたが口外しなかった。二人の理解者だったとも言える。その彼が遺体を発見したのは昨日の午前十時。二人が出かけた様子もないのに、異様に静かだったので、不審に思ったということである。二人のスリッパが勇介の部屋の前に並んでいたので、勇介の部屋のドアを叩いてみた。しかし一向に返事がない。更に物見を不安にさせたのはそのスリッパの並び方だった。まるで飛び降り自殺をする人が残す履き物ののように異様にきちんと丁寧に並んでいたのである。
「自殺」
その二文字が彼の頭にひらめいて、夢中で合い鍵を持ってきて鍵を開けたのだそうだ。カーテンはしまったままだった。二人が一つの布団で眠っていた。話しかけても、揺すっても反応がない。布団をはぐと二人の体に電気のコードが絡み合っているのがわかった。時間が来ると電流が流れるような仕掛けをし、電極を心臓にテープで貼り付けていたのが、後の調べで分かった。感電死である。
バンシューが事件のおさらいをする。
「睡眠薬を飲んで、感電死ねぇ。おまけに窓もドアも鍵がかかっていて、部屋の鍵は室内にあった。つまり密室。自殺でなければ、どちらかが持ちかけた無理心中というとこかしら。睡眠薬ってところは女の犯行っぽいよね。合い鍵を持っているのが大家だけなら、大家が犯人なんじゃないの」
「ところが、ドアの鍵は内側のノブを押してドアを閉めれば施錠出来るタイプだ。一度中に入ってしまえば、出る時に鍵はいらない。おまけに容疑者もいるんだ」
「誰。容疑者」
バンシューが身を乗り出すのを見て、中星は少し笑う。
「はは、バンシューの復活だね。」
「うるさいわね。四の五の言うと話を聞いてやらないわよ」
中星は六時間目に自分から申し出て、学校の応接室でに刑事からの事情聴取に協力していた。その聴取を担当したのが、若いのに白髪が目立つ武漢刑事だった。彼は以前からバンシューや中星たちとは知り合いでもあったので、事情聴取の合間に中星も武漢からいろいろと情報を聞き出していた。どっちが事情聴取されたのか分からない。ともかくそれによると話題に上がったのは三名だということだった。
白目善三。大高校の教師で生活指導部の主任、担当は社会科。匿名の投書を受けアパートに赴き、二人の同棲の現場を押さえる。教頭試験に合格しており、来年度からは管理職に登用される予定である。
高中勇一 勇介の義理の兄。勇介の両親は不妊治療を受けていたが、実子に恵まれなかったため、養子をとった。それが勇一だったが、十年後に勇介が生まれた。思春期に両親と仲違いをして別居中。市内の牛乳屋で住み込みでずっと働いている。独身。
東原京太。圭の幼なじみで自称婚約者。圭に対してしつこく求愛を繰り返していた。
バンシューが中星の話を整理すべく質問を挟む。
「東原って、二人が同棲していたことに気がつかなかったの。間抜けな奴だねぇ」
「最近ようやく気がついたみたいだ。白目に投書したのは東原なんじゃないかな。嫉妬に狂って、かわいさ余ってにくさが百倍ってケースだろ」
「でも、睡眠薬を飲ませたりなんて、親しくないと出来ないよ。東原は忌み嫌われる存在なんでしょ。そんな奴からもらったものなんて、絶対に口にしないと思う。このタイプの犯行は無理だわ。それよりも義理の兄さんがなんだって、容疑者になるのよ。第一、同棲に関して知ってたのかしら」
「隣人なのは知ってたみたいだけど、同棲まではどうかな。親子関係は悪かったみたいだけど、兄弟仲が良かったみたいだけどね。容疑者になる可能性としたら実は一番あるみたいなんだな。勇介の祖父ってのはまだ山形で健在なんだけど、いわゆる森林王ってやつでね。凄い資産家なんだって。親子関係はうまくいってなかったけど、祖父との関係は満更悪くもないみたいだし、まだ籍を抜かれた訳でもない。どうだい。犯人の目星はついたかい」
「あのね。わっかるわけないじゃないの。可能性が一番高いのは自殺なんでしょ。密室だからって『まだらの紐』のホームズだって現地に行かなきゃ、へっぽこな推理しかできなかったじゃないの。早計はいけません。現場へ行きましょ、現場へ」
バンシューは中星と純紀をせき立てた。
「えっ今から」
「理屈は後で。行動が先よ。さっ行きましょう」
バンシューは手近なところで生徒指導部を訪ねる。中には白目が落ち着かない様子で座ってハイライトの煙を吹かしていた。退勤時刻を一時間超えているはずだが、それどころではないのだろう。
「おっ川村か。残念だったな、芥女落ちたそうじゃないか」
ズキッと擬音が目に入るくらいのわかりやすい反応で、バンシューの動きが一旦停止した。中星と純紀がおろおろしながら立っている。バンシューは大きく息を吸い込むと、敵意むき出しの追及を始めた。
「私に女子大なんてそもそも似合わなかっただけですよ。実は高中くんと矢川さんのことなんです。ねぇ、先生」
「なんだね。話すことは別にないが」と、乱暴に煙草の火を消した。
「二人のことについて投書があったそうですけど。それって、いつ頃のことですか」
「そんなこと答える必要はない。それに君たちはどうせ前から知っていたんだろう」
「いえ、全く。クラスメートの中星くんが偶然それを知ったのが一週間前なんだそうです。だから悩んでるんですよ」
「投書したのが君でないなら、悩む必要はないだろう」
「自分が学校に投書したんじゃないかと、霊に疑われると困るって言うんです。祟られたら怖いんですって」
「心配いらない。これを見てみろ」机の引き出しから、一枚のコピーを取り出した。
「これが投書のコピーだ。現物は警察に提出してしまったが、一枚コピーを取っておいたんだ。この文字は中星には書けない」
「中星くんの字は小学生みたいですからね」と、バンシューがニンマリと笑う。
投書は封書ではなく、葉書だった。妙に個性のない文字で、簡潔に二人の同棲のことが書かれてあった。簡潔と言うよりは事務連絡に等しい素っ気ない文章だった。
「これが学校に配達されたのが二日前、今週の月曜日だった。その日の放課後に高中を呼び出して事情を聞いたが、あいつは否定した。しかし、怪しく思った私は夕べ家庭訪問をして、現場を押さえた。私がどうしたものかと学校への報告を一晩躊躇っているうちに、今日は二人とも登校していない。昼前には心中したという連絡があって、さっきまで大忙しだったよ。あの二人には悩む程の間もなかったと思う。結論を急ぎすぎるよ、今の子たちは」
「二人の同棲はどうして今までばれなかったんですか。住所が同じアパートだったら、すぐに分かりそうなものじゃないですか。先生たちは気がつかなかったんですか」
「高中が一人暮らしをしているのは分かっていた。あいつが両親と離れて残ったのは柔道のためだからな。それは有名な話だ。しかし矢川は親戚のおじさんのところに下宿していることになっていた。そのおじさんというのがアパートの大家のことなんだが、大家の自宅とアパートとは地番が違うだけじゃないんだ。」
行政区まで違う。いわば隣町だ。遊山荘は中町と外引町の境界際にある。遊山荘は中町だが、大家の物見一郎の自宅は外引町なのだ。実際は背中合わせになっているのだが、物見の家は南向きの一戸建て、遊山荘はその背中側に立つ二階建てのアパート。それぞれ両脇には別な建物が並んでおり、外観がまるで違う。中町側はアパート街だが、外引町側はどちらかといえば商店街となっている。物見の自宅は米屋であり、自宅と遊山荘は管理人用の廊下で繋がっているのであるが、それはアパートの住人や近所の人でもなければわからない。
「矢川は住所を大家の住所にして報告していたんだ。郵便物が大家のところに届いても、結局は矢川の元へ届く。何か問題でも発生しない限り、うちの学校は家庭訪問なんてしないから、今まで発覚しなかった。矢川は優等生だったし。高中も国体選手だったし。そんな二人が同棲していた挙げ句に、心中したなんて、大問題だ。学校の周りにはまだマスコミの連中が渦を巻いている。君たちもおかしなコメントを出さないことだ。」
逆に取材でもしてやろうという根性のバンシューは、にこりと笑って生徒指導部を後にする。部室に戻る道すがらバンシューは後から突いてくる二人を振り返る。
「次は現地調査ね。と言っても、遺体発見が今朝じゃとても私たちが近づける状態じゃないわね。司法解剖が終わって、お通夜にお葬式も斎場でやるしかないわね。中星くん。捜査は週末までお預けね」
土曜日。からりと晴れた青空。部活の練習が終わった午後。バンシューたちは遊山荘に向かう。が、歩いていけるような距離ではない。
「中星くん」
「はい」
「探偵料はつけにしておいてあげるけど、交通費は実費でいただくわ」
バンシューは中星にバス代を払わせる。純紀は助手と言うことで、彼女の分も中星が払うことになった。遊山荘近くのバス停で降りると、中星に案内させてバンシューと純紀が後に続く。純紀がしみじみとした口調で嘆く。
「山川さんって中学校が同じだったの。あまり親しい友達じゃなかったけど、あの人が同棲していたなんてショックだわ。信じられない」
「雰囲気からすると自殺なんだろうけどさ。中星くんは自殺じゃないっていうけど、本当のところは分からないわよね」
「バンシューもしてみたいと思う」
「自殺なんてゴメンだわ」
「違うわよ。同棲よ。同棲」
「同棲ねぇ。同居も結婚もぴんと来ないわ」
「先輩が東京で待ってるんでしょ」
「勝手に待ってるだけよ。あの先輩と私とはなんでもないんですからね」
バンシューは演劇部の卒業生から交際を申し込まれているのだが、彼女には全くその気がないのである。
中星が遊山荘を指さしたのと、純紀が、
「あれ、武漢さんじゃないの」とバンシューの手を引いたのがほぼ同時だった。
武漢刑事は一人で遊山荘から出てくるところだった。まだ、若いくせにその髪の毛がほとんど白髪という武漢は三人組の視線に気がついた。
「よっ中星。モテてるなぁと思えば、バンシューに純紀か」
武漢は柔道の国体選手だったので、スマートながらどこか貫禄がある。以前、市内で事件が発生したときにバンシューたちが捜査に協力したこともあり、周知の仲だった。武漢は柔道を通じて、亡くなった勇介とは面識があったらしい。バンシューは中星を押しのけて前に出る。
「ね、どうなったの。事件の方」
好奇心の塊というか、近所のオバサンみたいな身の乗り出し方だ。
「事件。…自殺だ」
一言で片付けられてしまい、三人は拍子抜けした気分。
「何故。何故、そうあっさりと言えるの」
「事故死じゃない。病死や自然死でもない。自殺か他殺かだが。さっき、署から連絡があってね。室内のドアノブとその鍵に高中勇介の指紋があったんだ。鍵なしでドアをロックする時に、ドアノブの中心にあるボタンを押して、ドアを閉めるタイプの鍵。つまり本人がボタンを押して、ドアを内側から閉めたってことだ。つまり自殺」
「何故」
「犯人が部屋の中にいたとしたら、逃げられないだろう。ドアノブには高中勇介の指紋しかなかったんだ」
すぐにムキになるのが武漢の癖である。このアタリがよくバンシューに利用されて、教えなくてもいい情報までも、つい彼女に引き出されてしまうのである。
「でも、鍵があれば外から閉めればいいんでしょ」
「高中の部屋の鍵は部屋の中にあった」
「それ一つってことはないでしょ」
「大家も持ってる」
「それだけじゃないでしょ。二人は同棲していたんだから、互いの部屋の合い鍵を作っていても、おかしくはないわ。その部屋にあった鍵は勇介くんのものだったの」
「バイクの鍵と同じキーホルダーにつけてあった。だから、間違いなく高中のものだろう。そうか、合い鍵が複数あった可能性もあるな」
武漢はあわてて遊山荘に向き直る。
「もう一回、大家に話を聞いてみよう。お前らも来るか」
物見一郎のはげた後頭部越しにネームプレートが見える。高中。物見は勇介の部屋の鍵を開ける。
「合い鍵ねぇ。私は分かりませんね。遺品の中から出てこなかったんでしょうか……。どうぞ」
中星は部屋の中に一番に入った。線香の香りがする。バンシューは家具を物珍しそうに見回す。
「さてと、中星くん。前は行ったときと変わったものはないかしら」
「変わりすぎていて分からないよ。ポスターから、食器棚の配置から換わってしまっている。あいつの私物なんかも既に親が整理してしまったんだな」
最後に入ってきた武漢が頭を掻いていた。
「そうなんだよ。親御さんたちがやってきて、めぼしい遺品は持っていってしまった。事件性は低いのでと言う判断があったせいだが、山川家の人も同様でね。お互い敵同士みたいだったよ。まっ親たちも同棲については知らなかったみたいだし、無理もないけどね」
バンシューは窓際のカーテンをめくりながら尋ねる。
「ねっ。武漢さんも自殺だと思うの」
「まあ、多分ね。合い鍵が存在したという確証はない。遺族も別にそのことに関しては何も言ってなかった。」
「じゃ、動機は」
「つまり同棲がばれたからだろう」
「そこが、そもそもおかしいよね」
武漢は眼を白黒させる。
「おかしいって、何が。同棲がばれる。親が反対する。別れるくらいなら、いっそ、あの世で」
「ナンセンス。おかしいわよ。ばれたかもしれないけど。誰からも反対されてないわ」
「前の日の夜に生徒指導部の先生が家庭訪問したそうじゃないか。そこで別れるようにいわれたんだろう」
「それはそうかもしれないけど、先生にばれたからって次の日の朝に死んだりするかしら。親にばれたわけでも、反対されたわけでもない。第一、あと半年で卒業よ。同棲を解消しようと、どちらかが転校しようと、半年後には結婚だって出来るのよ。それがどうして今死ななくちゃならないのよ」
黙って聞いていた大家が口を出す。
「若いってのは結論を急ぎすぎるのかもしれないね」
バンシューが大家に視線を向ける。じっと見つめる。間があく。
「大家さん。同棲を知っていたのに、何故黙っていたの」
「圭は私の姪だったし、小さい頃からかわいがっていた子だ。しっかりしたあの子のすることだから、全面的に信頼していただけさ」
さらに無言で物見を見つめるバンシュー。美少女のバンシューに見つめられると、年寄りでも慌てるのか、次第にどぎまぎしはじめた。バンシューは目をそらさない。
「この部屋の隣は、それに一階の間取りを教えてください」
「えっとですね。玄関は東を向いてます。東西に廊下があって、両脇に四部屋ずつ、六畳の和室があります。廊下の突き当たりは普段は施錠してありますが、私の自宅に繋がるようになっています。玄関から見て左手前が一号室。右手前が二号室になってます。高中勇介くんの部屋が五号室。圭の部屋は壁越し、といっても押し入れがありますけど、この向こう側で七号室となります」
「奇数番の部屋は南向きなんですね。北向きの部屋には四号室もあるんですね」
「あぁ、四ていう数字が不吉だなんて言う人もいるけど、私は気にしてないですね。この部屋の上の部屋は十三号室だけど、気にする人は入居しなきゃいいだけですからね」
「数字の吉凶なんて気にする人もいるのかしらね。非科学的だわ」
「でしょ。お嬢さん」
お嬢さんと言われてバンシューはご機嫌かと思えば、不機嫌らしい顔つきである。
「つまり、この押し入れの向こう側が矢川さんの部屋なんですね。すると、こっちの西側の壁はも壁一枚でお隣さんというわけだ。お隣の住人はどなたなんですか」
「共稼ぎの若夫婦が住んでます。近く赤ちゃんが生まれる予定なので、引っ越す予定ですがね」
「このアパートは男女も既婚も未婚もなんでもありなんですね。勇介くんは新婚さんの部屋と壁一枚だったわけですか。同棲したくもなるかもね。ねぇ、中星くん」
急に名を呼ばれて、中星がまごついていると、呼んだ理由は相槌の要求ではなかった。バンシューは思考の整理中に中星という無地のページを利用したいらしいのだ。
「なんで、二人はいつも矢川さんの部屋で寝ていたと思う」
「隣が壁一枚で新婚さんの部屋だったから」
「バッカじゃないの。なんでそうなるのよ。君はこのあいだ私に言ったじゃない。貴方がここに泊まりに来た時のことを」
「圭の部屋に二組の布団が置いてあったから」
「しかるに、二人はどうして勇介の部屋で死んでいたの。いや、寝ていたのよ」
中星が答えられそうにないので、矛先が武漢を向く。
「ねっ武漢刑事。二人は狭そうに一つの布団で寝て、死んでいたわけでしょ」
「ああ」と頷きながら、武漢は物見を見る。
第一発見者である物見も頷く。
バンシューが全員を見渡して、
「普段、勇介くんたちは圭の部屋で寝ていたんですよね。布団はそっちに二組ある。何故、死ぬときだけ、勇介くんの部屋を使ったのか…。おかしいわよね。おかしいわ」
バンシューは初めて事件に興味を持ったらしく、部屋をうろうろし始めた。といっても、六條間に五人の人間が立っているわけだから、狭苦しいといったらありゃしない。
「結局、他殺なんだろうけど、犯人が間抜けすぎるわ」
純紀がびっくりして、バンシューの腕を掴む。
「えっどうして。どうして、そう言い切っちゃうわけ」
武漢がニヒルに笑って、理由を促す。
「大家さんが証人よ。二人のスリッパがきちんと部屋の前に揃えてあったっていったでしょ。このドアは外開きよ。きちんと揃えて廊下に並べても、ドアを閉めるときにずれてしまうに決まってるじゃない」
「あっそうか」と、武漢はドアのそばに駆け寄って、それを開閉しながらうなずいた。
「と、ここまでは私だって、部室で中星くんの話を聞いたときに気がついてたわよ。スリッパが並んでいたのを見たのは大家さんだけだし、端から自殺、心中の線が打ち出されていたから、警察は見落としたのかしら。犯人同様の大間抜けってとこかしら」
武漢が流石にむっとするが、中星と純紀は感心している。バンシューが続ける。
「容疑者っているんですかね。中星くんが聞いたという人たちにアリバイって、あるんですか」
「あるようなないような。とにかく二人が睡眠薬を飲んだ、いや、呑まされたのは死ぬ6時間前だ。つまり火曜日の深夜。この時間帯にはたいていの人間は自宅で家族と寝ている頃だ。白目は自宅、高中の義兄は寮。東原は飲み屋をはしごして、自宅に戻ったのが三時頃だという事だが、どこで呑んだか記憶も定かでないし、裏も確実に取れたわけではない」
「つまり、アリバイのある人間は誰もいない。それは当然ですね。平日の夜なんだから。もっと不思議なのは殺人の動機のある者がいないということです」
武漢がメモ用紙をを閉じながら、
「動機はあるだろう。出世の妨げだったり、遺産の分け前だったり、愛情の裏返しとか」
「こないだ聞いた三人の動機なんだけど、動機として変なのよね。白目先生は生徒の不祥事が出世の妨げになるかもしれないけど、心中よりはましでしょ。高中兄の場合は父の遺産ではなくて、祖父の遺産でしょ。彼にはそもそも相続権なんてないのよ。祖父も父親も丈夫なんでしょ。勇介くんが死のうと生きようとまだまだお金にはならないでしょ。東原には二人に睡眠薬を飲ませるチャンスはなさそうよ。三人とも睡眠薬を手に入れるためには処方箋がいるから、そもそも足がつきやすいわ」
武漢刑事も首をひねる。勇介と圭の心中にしても、睡眠薬の入手先が不明だったようだ。
「そうなんだよ。医者の処方箋がなくては睡眠薬は手に入らない。関係者の通院履歴を調べても、特に疑わしいところはなかった。署に連絡したいな。物見さん、電話をお借りしたいんですが」
「では、私の自宅の方へどうぞ」
物見はポケットから合い鍵の束を出しながら、廊下へ出る。廊下の突き当たりのドアを開けて、自宅へ案内するつもりなのだろう。部屋にはバンシューたちが残された。
バンシューは武漢の戻るまでの間に、線香を上げて合掌する。しばし黙祷。黙祷が長いので、心配になった中星がバンシューの名を呼ぶ。
「バンシュー……」
「…………」
静かに目を開けるバンシュー。そして中星を見上げる。
「『黒猫』って知ってる?」
「黒猫?最近見てないな。時行の家にブラックっていう名の猫はいるけどね」
純紀が「えーっ、あの白い猫、そんな名前だったの。変」
バンシューが聞く相手を間違えたという思いを前面に押し出してから、純紀に聞き直した。純紀は人差し指を下唇の下に当てて考える。
「宅急便のことじゃないよね。エドガー・ア・ラン・ポーの小説の事かしら」。
「さすが、文学少女」
中星が「『黒猫亭事件』は横溝正史だから、江戸川乱歩じゃないぞ」と抗弁するが、バンシューは取り合わない。
「中星くん。そこにビニールの工具箱があるよね。その中に新品のトンカチがあるみたいだから、取ってくれないかしら」
バンシューはトンカチと言ったが、釘打ち用ではなく、コンクリートを粉砕するのに使うような重いハンマーだ。新品らしく値札まで付いている。中星がハンマーを握る。バンシューは純紀を振り返る。
「純紀は押し入れを開けてみて」
純紀が押し入れを開ける。押し入れは二段になっていて、上段はハンガーをかける鉄棒が渡してあり、洋服ダンスのようになっており、下段が寝具入れになっている。死体の寝ていたらしい布団が丁寧に畳まれて入っている。
「悪いけどそれを出しちゃってくれない」
「私が?」
「そっ、もっと嫌な役は中星くんに頼むから」
純紀はおっかなびっくり布団に手を伸ばす。まるで今にも布団の中から何か飛び出ししてくるような気がするらしい。
布団を部屋の隅に積み重ねると、バンシューはやっと立ち上がった。そして純紀を廊下の方に追い出してから、押し入れの下段に首を突っ込んだ。ごそごそと何かしていたみたいだが、押し入れの外に出ると、中星に向き直った。
「この押し入れの奥って、何故か壁紙が貼ってあるよね。この下の段の奥をハンマーで叩いてご覧」
「お前そんなこと言うけど、押し入れの壁の向こうは隣の部屋の壁だよ。向こうの部屋に抜けちゃうよ。トンカチで叩いたりしたら。抜けても知らないよ」
「中星くんは大道具だけあって、トンカチ握ると似合うじゃないの。でも、この押し入れは抜けないと思うよ。先ずは軽く叩いてみて」
中星は押し入れの中に、四つんばいになって、上半身を突っ込んだ。トンカチを振るう。
「あれ、変だな。中身が詰まっているみたいだな。ただの壁じゃないぞ。コンクリートの柱みたいだ」
「じや、思い切り、叩いてみて。責任取るからさ」
「本当だろうな、それ。じゃあ、大道具の中星様のトンカチ裁きをご覧に入れましょうか」
バンシューは中星の返事を聞かないうちに、廊下に飛び出して、ドアを閉めている。
純紀が不安な顔で、バンシューを見る。
「まさか……」
「たぶん……」
音を聞きつけた物見たちが廊下を駆けてくる。物見が慌てて、バンシューに詰め寄る。
「なんの音ですか」
「押し入れの奥を壊しているんです」
「よっ、よしなさい」
物見が叫んだ瞬間、部屋の中から中星の悲鳴があがった。その悲鳴を聞いて、武漢が部屋に飛び込む。物見は廊下に立ちつくしていたが、へなへなと腰が抜けたようになり、その場に尻餅をついた。物見の表情がすべて告白していた。
押し入れの奥が勇介の部屋だけ狭かったのは、そこに死体が埋められていたからだった。
コンクリートの裂け目から中星が見たのは白骨化した手だった。中星はぶるぶる震えながら、部屋からはい出してくる。それを見て純紀も気を失う。
勇介と圭の良き理解者だったはずの物見一郎が彼らを殺害した犯人だった。彼は五年前にアパートの住人だった女性を恋愛関係のもつれから殺害した。世間的には彼女が失踪したことにして、死体を密かに彼女の部屋の押し入れの奥に、コンクリートで埋めてしまった。彼女は睡眠薬による自殺未遂をおこなった過去があったため、失踪して再び服毒自殺をしたのではないかと警察も思っていたらしい。彼女を殺害した後で、彼女が所持していた睡眠薬を物見は隠匿し、彼女が睡眠薬を大量に所持した上で失踪したように偽装したのである。その薬が今回の事件に使用されたのだった。
物見の犯罪はずっと発覚しなかったのだが、最近になって勇介が押し入れの奥を執拗に気にするようになった。前の住人が失踪したことを物見に何度も問い質した。物見は勇介がコンクリート破砕用のハンマーを購入する場面を偶然目撃してしまった。勇介が壁を壊す前に何とかしないと自分の犯行が露見してしまう。焦った物見は二人のことを学校に密告し、勇介の気をそらし、二人を追いつめた。白目の帰った後、善後策を講じていた二人の相談に乗るふりをして、二人に睡眠薬を混ぜたコーヒーを呑ませたのである。
本来、二人を偽装心中に見せるのは圭の部屋のはずだった。死体のある押し入れのある部屋を心中現場にすることはリスクが伴うからである。しかし、睡眠薬を呑んだ勇介は自分の部屋へ戻っている時に寝てしまった。小柄な物見には勇介の体を運ぶことは出来なかったので、逆に圭を勇介の部屋に運ぶしかなかった。二人を殺害した後で、画竜点睛とばかりにスリッパを揃えておいたのが、敗因の一つ。もう一つは、考えるよりも早く、無責任に実行してしまう、直感ひらめき(思いつき)型探偵バンシューを見くびったことに尽きる。
「やぁ、ごめんねぇ。まさか、本当にあるなんて……思わなくてさ。今度は徳川の埋蔵金とかに挑戦してみようか」
中星と純紀とを両脇に支えながら、中秋の夕映え雲の下、バンシューは帰途についたのである。