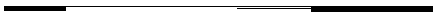翌朝、ひそかにロッカーを確かめると、ノートがなくなっていた。誰かのいたずらに引っかかったのかと思いつつ、未練たらしく金曜日の放課後を待った。「ミナミ」は金曜日にノートをロッカーに置いておく約束だったからである。金曜日、果たしてノートは戻っていた。
○月○日 タツヤの字はずいぶんじょうずになりましたね。ペン字でも習っているの。ミナミの家はお引っ越しをしませんでした。いなくなったのは私だけだったのです。私が今いるところは……教えたくありません。(ミナミ)
間違いなく、「ミナミ」の字だった。
次の日がみどりの日で休みだったので、自分は「ミナミ」の家を探してみることにした。町のあちこちに鯉のぼりが飾ってある。男の子のいる家というのは誇らしげに鯉のぼりをあげるものだなぁなどと、年寄りじみたことを思いながらも、新緑の季節の風は妙に心地よい。交通量が多い交差点の角に「ミナミ」の家は確かに昔のたたずまいのまま、そこにあった。表札をみると原田という姓である。確かに「ミナミ」の家は引っ越してはいないようだった。それなのに何故、彼女だけが急に学校からいなくなったのだろう。お別れ会も、転校の挨拶もしないで、彼女だけいなくなるなんて今考えてみると納得できない。学期の途中の転校だって珍しくもない環境だったのだから、絶対にクラスで送別会をするはずなのに。郵便受けの表示を見ると家族全員の名前が並んでいる。しかし、「ミナミ」の本名、美波子だけがない。いや、ないのではなく、消されていた。消されたあとが残っている。それもかなり昔に消されたようだ。家を尋ねるわけにもいかず、まごまごしていると、買い物かごを下げたおばさんに声をかけられた。
「あなたは貴志君でしょう。立派になって。今、西小の先生をしてるんですってね。ご無沙汰しています。覚えてませんか。私、美波子の母です。」
「ミナミ」の少女時代は不幸だったといえるだろう。十歳を過ぎてから養子に出されて、なじめなくて苦労したらしい。けれども養家の親たちの深い愛情に、次第にうち解けることができた。今では両親が四人もいる気持ちで元気に過ごしていて、両家の交流自体も盛んだという。さらに、自分との再会ができて、これまたひどく喜んでいるらしい。最近の不幸といえば、コンタクトレンズをなくしたことだけだったということだ。
「君がミナミだったんだね。いつも眼鏡なんかかけていたからわからなかったよ。」
「ミナミ」はにっこりと微笑んだ。そして抱えていた古紙の束を下ろし、眼鏡を外した。
「やっと気がついてくれたのね。タツヤくん。」